「TOEICリーディング問題は、Part7の長文が全然解き終わらない…大量の塗り絵をしてしまう」
TOEIC体験者の多くの人が一度は抱える悩みではないでしょうか。
TOEICリーディング問題はその分量と試験時間がアンバランスではないかと愚痴を言いたくなるほど、解くのに時間が足りません。
大学受験などと同じ感覚で長文を精読して読み進めると、塗り絵 (時間切れで解けなかった問題を適当にマークすること) を量産する結果になります。
スコアアップを目指すのであれば、Part7 をしっかり対策して、限界まで塗り絵の数を減らしていかなければなりません (理想はゼロ) 。
ただやみくもに読んでいくのではなく、読み方の方針を立ててそれを実践してことで、効率よくスピーディーに解き進めていきましょう!
この記事では、最大の壁といわれる Part7 を攻略するための対策をさまざまな視点から紹介していきます。
TOEICリーディング Part7 の時間配分について
まずは時間配分から。Part5 で10分、Part6 で8分の合計18分を使ったすると、総時間は75分ですから、Part7 は残りの57分で解くことになります。
そしてこのパートは「シングルパッセージ問題」と「マルチプルパッセージ問題」の2つの構成に分かれています。
シングルパッセージ問題とは、文字通り1つの長文を読解する問題で、全部で10題、問題数は全部で29問あります。
一方マルチプルパッセージ問題とは、複数(2~3つ)の長文で構成された問題です。
それぞれの文章が互いに関係し合って、ストーリーが完結しています。こちらは全部で5題、問題数は全部で25問あります。
Part7に使える時間は57分、問題数は合計 29 + 25 = 54問ですから、平均で1問につき約1分で解いていく計算なります。
この時間配分だと、もしも長文を隅から隅まで精読して、全てを完璧に理解をしながら解き進もうものなら、普通は時間内に解き終われません。
ネイティブレベルの人が解くのならまだしも、私を含む一般の受験者の場合は、もう塗り絵の嵐で試験が終わることでしょう。
やはり解答に至るまでの手順について適切な対策を立てて、それ実践する練習を積むことが大切です。
Part7の具体的な対策について
では Part7 についての対策のポイントを挙げます。
- どんな種類の文章なのかを確認する
- 問題を2問先に確認してから、本文を読み始める
- 設問文の中で定型文と考えられるものは、あらかじめ覚えておけばよい
- 本文は、全て読むべきか?拾い読みでよいか?
- 場面の光景を頭の中でイメージしながら読み進めていく
- あとに重要な文章が続くことを示す語句に敏感になる
- 分からない構文や単語にも慌てず、推測し、無理なら読み飛ばす
- 固有名詞や、数字などに注意!
- 返り読みをしない
以下に、それぞれの説明をしていきます。
どんな種類の文章なのかを確認する
まず1番最初に、今から読む文章がどんな種類のものなのかを確認することから始めましょう。
それを確認する場所は、先頭です。たとえば、
Questions 181-185 refer to the following advertisement and letter.
「問題181~185は、広告と手紙文に関するものです。」
のように、先頭で、親切にも文章の種類についてきちんと説明してくれているのです。
ここをまず確認することで「何を読むことになるのか分からない」という不安から解放されて、安心して読み始めることができます。
小さなことに感じる人もいるかもしれませんが、この安心感と英文に対する心づもりというのは、心理的にかなり心強いものだと思います。
問題を2問先に確認してから、本文を読み始める
次に、本文を読み進めていく前に、問題を2問ほど確認しておきましょう。 何が問われているのかだけでも確認しておけば、本文を読んでいて
「あっ、これはさっきの問題で問われていた場面だ!」
と気付くことができます。
逆に、文章を全部読み終えてから問題へ進んだ場合は、
「あっ、これは確かこの辺りに書いてあったような・・・」
と、該当箇所を探す時間が必要になってしまい、大きな時間のロスにつながりますので、注意しましょう。
なお、ここで「2問ほど確認」と、1問目だけではなくて2問目まで確認が必要としたのには理由があります。
1問目というのは文章全体のテーマを聞いてきたりなど、ある程度文章を読み進めないと答えがハッキリしないケースが多いからです。
頭から読み進めて1番最初に答えが判明するのは2問目から、というケースが多いでしょう。
そして、2問目の答えをマークしたら、今度は3問目の問題を確認してから続きを読み進めていく、という手順で繰り返していきましょう。
設問文の中で定型文と考えられるものは、あらかじめ覚えておけばよい
Part7 の各設問文を見てみると、同じ書かれ方をした設問が多くみられます。たとえば、
In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong?
” ---------------”
- (A) [1]
- (B) [2]
- (C) [3]
- (D) [4]
この設問の英文 (それに、選択肢の形も) を見た瞬間に
「あ、文挿入問題だな。」
と一瞬で判断できるようになるためにこのような定型文のような設問文はあらかじめ暗記しておきましょう。
こういう小さな時間の節約が積もり積もって、大きな解答時間の短縮が達成できるのです。
(設問の訳)「下記の文は、[1] ~ [4] と記された位置のうちどこに挿入するのが最適か。」
他にも、
- What is the main purpose of the ~ ?
「~の主な目的は何ですか?」 - What is indicated about ~ ?
「~について、何が示されていますか?」
なども、頻出の定型文の設問です。覚えておいて決して損はありません。
なお、この頻出の選択肢を覚えてしまうという手法は、リスニング Part3・4 を解く際にも有効です。
本文は、全て読むべきか?拾い読みでよいか?
市販の Part7 対策本などを読むと「本文は全てを読む必要などなく、問題に関係する部分のみを拾い上げて読むべき」という主張を見かけます。
確かに、本文から問題に関係する部分を瞬時に見つけられる能力を持っている人なら、その方法でいけば時間をかなり短縮できるでしょう。
しかし、個人的に感じるのは、そのような読み方ができる人は、もうすでに英語の能力がある程度高い人たちに限られるのではないでしょうか。
たとえば日本人なら、日本語の文章を読むときに、自分の興味がある部分や知りたい部分だけを記事の中から拾い上げて読むという芸当ができます。
ですがそれは、私たちが日本語にとても慣れていて、文字を見たときに何について書かれているのか瞬時に判断できるから可能なのでは?
だとすれば、英語のノンネイティブである普通の英語学習者が、英語の記事の中から必要部分だけを即座に抜き出すのは困難だと思われます。
少なくとも私がこの方法で問題演習を試みたときは、その必要な部分を探し出すのにかなり手間取りました。
結局、最初から普通に読んで内容を理解していったときよりも、解くのに時間がかかってしまったのです。
解くのに必要な部分を探すということは、結局、あらゆる候補の箇所をチェックしていかなければなりません。
すぐに見つかればラッキーですが、なかなか見つからないときは、まだ本文の全体の意味がつかめていない状態なので、焦りが生じてきます。
そして、最終的に選んだ解答についても、自信がなかなか持ちにくいのではないでしょうか。
「これが正解だと思うけど、もしかしたら読んでない箇所にひっかけの内容が書かれていないだろうか?」
などという気持ちが沸いてくる可能性もありえます。
私は、自身の体験からこの読み方は現在では行っておらず、普通に、本文の先頭から最後まで読み進めるようにしています。
やはり、本文全体の意味がとらえられていたほうが安心感があり、しかも解答に自信が持てます。
もちろん、拾い読みが性に合っていると感じる方なら別ですが、そうでないなら、文頭からメリハリをつけて読んでいくほうをおススメします。
場面の光景を頭の中でイメージし、映像化しながら読み進めていく
よくある悩みの1つに「英文を読み進めていくうちに、前に読んだ文の内容をどんどん忘れていってしまう」というのがあります。
人間なので忘れてしまうのは仕方がないことですが、できるだけ忘れる時間を延ばして、問題を解き終えるまでは記憶を維持できる方法があります。
それが「英文の内容を頭の中でイメージして、映像化しながら読んでいく」という方法です。たとえば、
He goes fishing every Sunday morning.
「彼は毎週日曜の朝、釣りに行く。」
という文章の場合、読みながら、「彼が釣りをしている姿」を頭の中でイメージ (映像化) していくのです。
彼の顔や表情、釣りのスタイル、釣りをしている場所などの細かいことは、あなたの自由な発想で大丈夫です。
そのように文の内容がイメージされて映像化されると、印象に残りやすく、記憶を維持しやすくなります。
私たちが昔の想い出を思い出すとき、文字が頭に思い浮かぶでしょうか?いいえ、その想い出の光景 (映像) が浮かんでくるはずです。そんな感じです。
そして、のちに設問でこの箇所が問われたときに、すぐにイメージしていた映像が頭の中に呼び戻されて、解答することができるようになるのです。
この「言葉をイメージして映像化する」という手法は、
- 新しい単語・熟語を覚えるとき
- TOEICリスニング Part3・4
などでも大変役に立つ対策法になるので、イメージするクセをつけるようにしましょう!
あとに重要な文章が続くことを示す語句に敏感になる
日本語の文章の場合でも、たとえば「つまり、~」・「しかし、~」・「実は、~」などの言葉の後には重要な内容が続きますよね?
これらの言葉の後には、筆者や話者が相手にしっかりと伝えたい内容が含まれるわけです。
英語でも同じことが言えます。
- 「つまり」→「therefore」
- 「しかし」→「however」
- 「実は」→「in fact」
などを文中で見つけたら要チェックで、その後に続く内容をより深く理解・記憶するようにしていきましょう。
そして、このことはリスニング問題でも同様です。問題でその場所が関係するか、直接問われる可能性が高いです。
上記のような単語は他にもたくさんあります。その他の具体例についても、今後紹介していきたいと思います。
ちなみに「for example(たとえば)」や「such as(たとえば~のような)」などの後は具体例が続くので、逆にサラッと読めばよいでしょう。
このように、文章中には重要な箇所で慎重に読み進めるべきところと、サラッと読んだり、読み飛ばしてもよい箇所などが混在しています。
それらを判別できるようになって、メリハリのある読み方をすればより効率的に、スピーディーに読めるようになるでしょう。
分からない構文や単語にも慌てず、推測し、無理なら読み飛ばす
TOEICに向けて十分に準備をしてきたとしても、本番ではどうしても分析できない構文や、知らない単語が出てくることはあると思います。
そんなときは決して慌てることなく、「分からない部分は、あって当然!」と気持ちを切り替えてください。
分からない箇所が少々あっても、大体の問題は解けてしまいます。そう心に言い聞かせて、本番では気にしないようにすることです。
そして、訳せないところは前後の文脈などから推測をしてみましょう。それで、推測しても思い浮かばないときは…
読み飛ばしましょう!
ハッキリ言って、1つの文章にこだわっている時間などないです。1つの場所に固執している時間を、次の文章を読む時間に譲ってあげてください。
こうした割り切りができるかどうかが、時間の足りないリーディング問題で最後の問題まで辿り着けるかどうかの分かれ道になるでしょう。
固有名詞や、数字などに注意!
英文の中には人名や組織名など、たくさんの固有名詞や、いろいろな数字が登場します。これらは設問文や選択肢によく出てくるので、要注意です。
設問文などに出てきたときにすぐに該当箇所を探し出せるよう、固有名詞や数字は、その場所に鉛筆や消しゴムなどを置いて示しておきましょう。
そうしておけば、すぐにその場を再チェックすることができます。
ちなみに、TOEICでは問題用紙への書き込みが禁止されています。なので、代替措置としてこの方法をおススメします。
書き込めれば、それが一番楽なんですがね…。
返り読みをしない
おそらくリーディング問題において、塗り絵を可能な限り減らす(理想はゼロ)ための最大の秘訣が、この「返り読みをしない」ことでしょう。
これまで説明した他のPart7対策ポイントは、意識さえすれば比較的すぐに実践できてしまうことばかりでした。
ただ、この「返り読みをしない」という対策は、身に付けるのにある程度時間がかかるかもしれません。
というのも、私たち日本人は、学生時代の勉強や受験勉強の際に、返り読みをする習慣を身に付けてきたのが普通だからです。
では、まずは返り読みとはどういう読み方なのかについて説明していきます。
さて、ここでいう「返り読み」とは、
「まず一文を最後まで読み終えてから、再び先頭に戻り、日本語としてふさわしい訳を考えながら理解していく」
という読み方をいいます。学生時代、そんな風に英語を訳していませんでしたか?
確かに私たちは日本人ですから、日本語に訳すときには日本語の文法で整えられた形に整理して意味を理解したほうが分かりやすいでしょう。
それに、学校のテストや大学受験などで「以下の英文を日本語訳せよ」という問題の場合はそうやって解答するのが普通ですし、そうするべきでしょう。
しかしながら、TOEICのようなスピード読解を必要とする場合や、リスニングする際には、振り返る時間的な余裕はありません。
そのため、返り読みをしてしまうこれまでのクセを取り除いて、
「英語を英語の語順のまま、理解していく」
という新しい体質を手に入れる必要があるのです。
では、具体例を挙げて、返り読みと、英語の語順のまま読んでいく方法の比較をしていきましょう。
< 返り読みの場合 >
The Quest Gallery in Osaka City will host its annual photography contest this spring.
この英文を返り読みをする場合は、まずは TheQuest から this spring までを全部読み終えてから、
「これは The Quest Gallery in Osaka City までが主語で、will host が動詞、its annual photography contest が目的語で、this springが副詞だな。
だから、意味は『大阪市のクエストギャラリーは、今春、年次写真撮影コンテストを主催します。』だな。これでよし!」
といった感じで読んでいきます。日本語訳は、単語を日本語として分かりやすい語順に並べ換えて、整理されたものになっています。
これが、返り読みです。
< 英語の語順のまま読んでいく場合 >
The Quest Gallery in Osaka City will host its annual photography contest this spring.
一方、この英文を英語の語順のまま読んでいく場合は、
「The Quest Gallery『クエストギャラリー』、in Osaka City『大阪市内の』、will host『主催する』、its annual photography contest『年次写真撮影コンテスト』、this spring『今春』、だな」
これで終わりです。つまり日本語訳は
「クエストギャラリー、大阪市内の、主宰する、年次写真撮影コンテスト、今春」
となります。どうですか?これでも十分、英文の意味は理解できるのではないでしょうか。
英語と日本語では文法的に語順が全然違うためにこのような訳し方になりますが、意味をとるだけなら、この語順でも問題ないわけです。
返り読みをした場合と比べて、頭の中で考えなければならない分量が全然違うことが明白ですよね。
当然、語順のまま読むほうが断然スピーディーに読めます。
また、リスニングのように読み直しができない場合でも、話の内容について行くことが可能になります。
これまで返り読みを続けてきた方が語順のまま理解する方法に変更する場合、最初はかなり違和感を感じると思います。私もそうでした。
少しずつでいいので、たまには返り読みをしてしまうそんな自分を許しながら、返り読みのクセを取り除いていきましょう。
なお、英語の語順のまま理解していくための練習方法としておススメなのが「音読」なのですが、こちらは今後の記事で紹介していきたいと思います。
英語を理解するのにスピードが要求される場面では必須ともいえる、この
「英語を、英語の語順のまま理解する」
という読み方・聞き方で、TOEICの壁をぜひ乗り越えていただきたいと思います。
まとめ
この記事は、以上となります。Part7 の解き方について、簡単にまとめると…
まず、問題文の先頭を見て、どんな種類の文章かを確認します。次に、先に問題を2問分読んでおいてから、本文を読み始めます。
本文読解中、先に読んでいた問題に該当する箇所を発見、解けたら、次の問題を読み、再び本文に戻ります。これを繰り返していきます。
ちなみに受験テクニックの1つとして、設問文の中で定型文と考えられるものは、解く時間を短縮するためにあらかじめ覚えておきましょう。
そして本文を読んでいる間は、書かれていることを頭の中でイメージして、映像化します。これで、記憶を強化できます。
また、本文中に in fact などの「あとに重要な文章が続くことを示す語句」が見つかったら、続きの文は要チェックです。出題の可能性が高いです。
加えて、固有名詞や数字は問題に関係しやすい箇所なので、チェックしておきます。
そして、分からない構文や単語が出て来ても慌てず、まずは推測を試みて、できなければ読み飛ばしていきましょう。
私は、本文は拾い読みではなく、きちんと最初から最後まで読み通すことをおススメします。ただし、メリハリを付けた読み方で。
そして最後に一番大事な点を。読む時間を短縮するために、「返り読みをしない」クセをつけましょう!
たくさんの対策を紹介しましたが、これらを実践することで塗り絵を限界まで減らし (理想はゼロ) 、大幅なスコアアップを果たしてくださいね!
Part7 を制する者は、TOEICを制します!
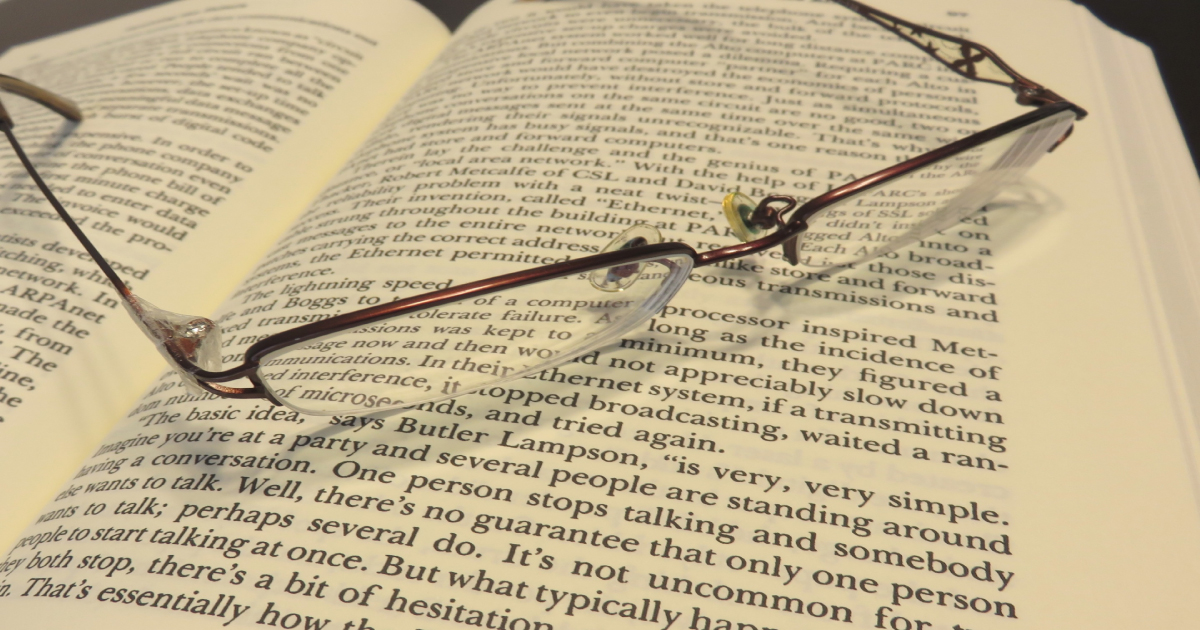


コメント
[…] ● 時間内に問題が解き終わらない (たくさん塗り絵してしまう・・・)● Part5 の短文穴埋め問題をスピーディーに解くにはどうすれば?● Part6 の長文穴埋め問題を解くコツって?● Part7 の読解問題を効率よくスピーディーに解くにはどうしたらいい? […]