「時間内に問題が解き終わらない! たくさん塗り絵してしまう・・」
おそらく TOEICのリーディング問題に取り組んだことがある人のほとんどが、同じような悩みを抱えるのではないでしょうか。
特に Part7 の読解問題のボリュームがかなりのものです。
最初は短めで読みやすいシングルパッセージ問題(1つの長文)から始まります。
ところが、どんどんと読む量は増えていき、最後には「マルチプルパッセージ問題 (2~3つの長文) 」 という1番長い文章が、5題も登場します。
受験勉強のときのような読み方をしていると、とても時間内に全てを解き終えることはできないでしょう。
結果として、テスト終了間際に塗り絵 (時間が足りずに解けなかった問題を適当にマークすること) をしまくることに…
かく言う私ももちろん同じ悩みを抱えていた1人です。
初めて受検した2020年11月の試験では、なんと100 問中25問も塗り絵してしまうという散々たる結果に終わりました・・・。
そこから一念発起して、あらゆる勉強法を研究して実践していった結果、3ヶ月後の2021年2月の試験では、塗り絵は10問まで減らすことができました。
15問減らせたということは、マルチプルパッセージ問題3題分ということなので、3ヶ月の対策だけでもかなりスピードを上げることができました。
そして2022 年1月現在は勉強法や解法に磨きをかけ、さらに読むスピードがアップしているので、 もうほとんど塗り絵の心配はしておりません。
ここでは、実体験として私自身が読み解くスピードがかなり速くなったと実感した方法を紹介していきます。
TOEICリーディング:各パートの時間配分を決める
まずは、リーディング問題全体の試験時間75分をどのように使っていくのかを検討しましょう。
リーディン グ問題は Part5 (短文穴埋め問題)、 Part6 (長文穴埋め問題)、そして Part7 (読解問題) の3つのパートに分かれ ています。
なので、各パートについてそれぞれどれくらいの時間を割り振るべきかを決めるところから始めましょう。
結論から言うと、
Part5 は10分、 Part6 は8分、そして最も解くのに時間のかかる Part7 には57分
の時間を割り当てることを提案します。以下、各パートごとに時間の使い方と対策法を説明していきます。
TOEICリーディング:Part5 (短文穴埋め問題)への時間配分と対策
Part5 は 「短文穴埋め問題」 です。 学生時代のテストなどでよく見慣れた形式の文法問題になります。
選択肢には
「同じ単語で品詞が異なるものがズラッと並んでいて、適切な品詞を選ぶ問題」や、
「選択肢に動詞の原形、過去形、過去分詞形などが並んでいて、適切な活用を選ぶ問題」
など、いろいろな形式の問題があります。
だいたいどの問題も、高校までの基本的な文法知識がしっかりしていれば、解くのにそれほど時間はかからないでしょう。
Part7の読解問題に多くの時間を残しておくためにも、できれば1問20秒、全部で30問あるので、1問20秒 × 30問 = 合計10分で解き終えられれば理想的だと思います。
ただしこのスピードで解くためには、当然ながら基本的な文法知識が備わっていなければいけません。
特に「品詞」や「文型」 などを正確に理解して、文の構造を正しく分析する必要があります。
最初は1問20秒というのはかなりハードルが高く感じられると思います。ほとんど選択肢で悩んでいる時間はないでしょう。
ですが、後に紹介する解法などを問題集などで実戦練習して問題の形式に慣れていけば、どんどんスピードは上がっていくはずです。
なお、あくまで「平均で1問20秒」ということなので、問題の難易度によって差が出てきます。
中には見た瞬間に解けてしまう問題もあり、早ければ8秒くらいで片付けられる問題もあるでしょう。
そういう問題はできるだけ早く処理して、比較的考えさせられる問題のために時間の貯金をし、最終的に全体で平均20秒程度になれば理想でしょう。
Part5の効率の良い解法とは?
では、実際に問題を解く際にどういった点に注意したら効率が良いのかについてですが、 ポイントは、
- 空欄と無関係と思われる部分は、サッと流して読む
- 空欄の前後にヒントがあることが多いので、見逃さない
この2点を意識して解いていけば、無駄な時間をかけずに済むでしょう。以下、説明していきます。
Part5 対策:空欄と無関係な部分にこだわらず、空欄の前後をチェック!
では、実際の問題形式を見てみましょう。
A proposal to hire some employees will be considered at the next ——- scheduled board of directors.
(A)regulate
(B)regulation
(C)regulating
(D)regularly
まずは、英文を先頭から読んでいきます。
A proposal to hire some employees
次の単語が will なので、ここまでが主語Sだと判断します。ところで、この「hire」という単語の意味は分かりますか?
この単語は学生時代にはあまりなじみのなかった単語だと思いますが、TOEICにはとてもよく出てくる単語です。
知らなかったとしても全然不思議ではありません。
ではなぜ今、この単語に注目したかというと、このことを伝えたかったからです。つまり…
「空欄と無関係と思われる部分にはこだわらずに、サッと読み流す程度でよい」
ということです。
今回の例では、空欄の箇所は英文の後半にあって、主語の内容が直接に関係しているとは考えにくいです。
なので、空欄に影響を与えていないと思われる部分については、こだわらずに、分からない箇所はそのままにして読み進めればいいのです。
今回の主語 A proposal to hire some employees で、もし hire の意味が分からなければ、そのまま無視して、
「従業員を数人~するという提案」
これだけ分かれば十分にこの問題は解けます。なんなら、employees も分からずに
「~するという提案」
しか意味が取れなくても、問題は解けるのです。もっと極端に言えば、主語が全て意味不明だとしても、この問題は解けます。
だって、空欄に影響を与えない部分だから。
Part5の英文を隅から隅まで精読して読もうとすると、ネイティブレベルでない限り1問20秒以内になんて解けません。
メリハリのある読み方をして、大事な部分とそうでない部分との読み方に差をつけることが大切です。
それでは、その「大事な部分」はどこにあるのでしょうか?それは、
「空欄の前後の部分」
になります。
上の例の続きを読んでいきましょう。
will be considered at the next ——- scheduled board of directors.
will be considered が動詞Vの部分で、その後に前置詞の at があるので、ここから前置詞句になってくると考えられます。
もしもその前の動詞 considered が分からなかったとしても、気にせずに読み進めてもらって大丈夫です。
そして今回の空欄の前後は、at the next ——- scheduled board of directors ですね。ここを正しく分析できるかどうかです。詳しく見てみましょう。
空欄の前に the が見えます。ということは、the のあとに名詞が続くと考えられます。
ただ、次の単語は next です。これは「次の~」という形容詞かなと判断して、では空欄にこそ名詞が入るのではと考えるのが普通でしょう。
名詞なら、選択肢(B)の regulation を入れて、the next regulation という名詞のカタマリを作って、ハイ終わり、としたいところです。
ですが、空欄の後も念のために確認してみると、
scheduled board of directors「予定された役員会議」
と、これまた名詞のカタマリが存在しているではありませんか。
もしも the next regulation で名詞のカタマリを作ってしまうと、その後のもう1つの名詞のカタマリがポツンと取り残されてしまいませんか?
ここで「あれ、おかしいな?」と考えられたら、シメたものです。
そこで、もう少し視野を広げて the のもう少し前を確認してみると、前置詞の at が目に入ってきます。
前置詞のあとに来るのは名詞と相場が決まっています。ということは…
「もしかしたら、前置詞 at の後は、大きな1つの名詞のカタマリになっているのでは?」
と考察できれば、もう正解できたも同然です。そうです、ここでは
at the next ——- scheduled board of directors.
この赤文字の部分全体で、1つの名詞のカタマリとなっているのです。
ということは、この中で名詞の部分は board of directors「役員会議」ですね。
そしてその前にある the next ——- scheduled は修飾語の部分となり、全体で
「 next ——- scheduled な役員会議」
と考えられますので、正解は、 scheduled「予定された」という形容詞を修飾することができる副詞の(B) regularly「定期的に」となって、
the next regularly scheduled board of directors「次回の定例役員会議」
という大きな名詞のカタマリが完成するわけです。
なお、全体の意味は「従業員を数人雇うという提案は、次回の定例役員会議で検討されるだろう。」です。
いかがでしょうか?空欄の前はサッと流して読んで、空欄の前後をチェックするだけで、正解にたどり着けましたね。
主語の部分がどうなっているかなど、この問題では別にどうでもよかったのです。
このような効率の良い解き方を身に付けていくことで、大幅なスピードアップを果たせるのです!
TOEIC リーディング Part6 (長文穴埋め問題) への時間配分と対策
Part6 は「長文穴埋め問題」です。 長文のところどころに空欄があり、それを埋めていく問題です。
長文は全部で4題出題されるので、1題4問 × 4題 = 合計16問を解きます。
ここでも Part7のことを考えて、1問30秒 ×16 = 合計8分で解き終えられれば理想的でしょう。
Part6 は英文の大意をザッとつかみながら読んでいく
対策としては、Part5 と同じ解法で解ける問題も多いのですが、中には前後の文章の内容を理解していないと正解を選べない問題も多々みられます。
やはり1文目からちゃんと読み進めたほうが、結果として選択肢で必要以上に悩む必要がなくなり、解くスピードが上がることにつながるでしょう。
ただし、全ての英文を完璧に理解できないと問題が解けないというわけではありません。
Part7 の長文読解問題よりもザッとでいいのでスピードを重視して読んでいき、文章の大意だけでもつかんでいきましょう。
そうすれば、選択肢でそれほど悩むことはないと思われます。
Part6 の文挿入問題はどう対策する?
また、問題の中には
「この英文を挿入するにはどの箇所が適当か?」
という文挿入問題も登場します。これも、文の大意さえつかめれば解ける問題ばかりです。
ただ、英文を読み進める前にこの手の問題がないかあらかじめ確認して、あればその英文の意味内容を理解しておくのがよいでしょう。
どのみち読まないといけないのですから、最初に読んでおいて頭の片隅に入れておきましょう。
すると、文章を読んでいるうちに
「あ、さっき読んだ文はここに入れたらしっくりくるな!」
とピンとくることがよくあるので、おススメです。
TOEIC リーディング Part7 (読解問題) への時間配分と対策
さて、いよいよ最大の壁である Part7 読解問題です。
このPart をどのように対策していくか次第で、塗り絵の個数の多少(理想はもちろんゼロ)が決まります。
やみくもに読んでいくのではなく、読み方の方針を立ててそれを実践してことで、効率よくスピーディーに解き進めていきましょう。
まずは時間配分から。Part5 で10分、Part6 で8分の合計18分を使ったすると、総時間は75分ですから、Part7 は残りの57分で解くことになります。
そしてこのパートは「シングルパッセージ問題」と「マルチプルパッセージ問題」の2つの構成に分かれています。
シングルパッセージ問題とは、文字通り1つの長文を読解する問題で、全部で10題、問題数は全部で29問あります。
一方マルチプルパッセージ問題とは、複数(2~3つ)の長文で構成された問題です。
それぞれの文章が互いに関係し合って、ストーリーが完結しています。こちらは全部で5題、問題数は全部で25問あります。
Part7に使える時間は57分、問題数は合計 29 + 25 = 54問ですから、平均で1問につき約1分で解いていく計算なります。
この時間配分だと、もしも長文を隅から隅まで精読して、全てを完璧に理解をしながら解き進もうものなら、普通は時間内に解き終われません。
ネイティブレベルの人が解くのならまだしも、私を含む一般の受験者の場合は、もう塗り絵の嵐で試験が終わることでしょう。
やはり解答に至るまでの手順について適切な対策を立てて、それ実践する練習を積むことが大切です。
Part7の具体的な対策について
では Part7 についての対策のポイントを挙げます。
- どんな種類の文章なのかを確認する
- 問題を2問先に確認してから、本文を読み始める
- 場面の光景を頭の中でイメージしながら読み進めていく
- あとに重要な文章が続くことを示す語句に敏感になる
- 分からない構文や単語にも慌てず、推測し、無理なら読み飛ばす
- 返り読みをしない
以下に、それぞれの説明をしていきます。
どんな種類の文章なのかを確認する
まず1番最初に、今から読む文章がどんな種類のものなのかを確認することから始めましょう。
それを確認する場所は、先頭です。たとえば、
Questions 181-185 refer to the following advertisement and letter.
「問題181~185は、広告と手紙文に関するものです。」
のように、先頭で、親切にも文章の種類についてきちんと説明してくれているのです。
ここをまず確認することで「何を読むことになるのか分からない」という不安から解放されて、安心して読み始めることができます。
小さなことに感じる人もいるかもしれませんが、この安心感と英文に対する心づもりというのは、心理的にかなり心強いものだと思います。
問題を2問先に確認してから、本文を読み始める
次に、本文を読み進めていく前に、問題を2問ほど確認しておきましょう。 何が問われているのかだけでも確認しておけば、本文を読んでいて
「あっ、これはさっきの問題で問われていた場面だ!」
と気付くことができます。
逆に、文章を全部読み終えてから問題へ進んだ場合は、
「あっ、これは確かこの辺りに書いてあったような・・・」
と、該当箇所を探す時間が必要になってしまい、大きな時間のロスにつながりますので、注意しましょう。
なお、ここで「2問ほど確認」と、1問目だけではなくて2問目まで確認が必要としたのには理由があります。
1問目というのは文章全体のテーマを聞いてきたりなど、ある程度文章を読み進めないと答えがハッキリしないケースが多いからです。
頭から読み進めて1番最初に答えが判明するのは2問目から、というケースが多いでしょう。
そして、2問目の答えをマークしたら、今度は3問目の問題を確認してから続きを読み進めていく、という手順で繰り返していきましょう。
場面の光景を頭の中でイメージしながら読み進めていく
英文を読み進めている間は、ただ文字を追って意味を理解していくだけではなくて、
そこに書かれていることを頭の中でしっかりイメージして、映像化していく
という作業を同時進行させていきましょう。
ただ書かれていることを理解するだけだと、その時はそれで満足できるのですが、なかなか記憶に残りにくいものです。
文章を読み進めていって新しい情報がどんどんと入ってくると、前の情報の記憶が思い出せなくなってしまった経験はありませんか?
個人差はあれど、誰でも経験があると思います。そして、これは学術的な根拠はないものですが…
「文字それ自体には感情や景色というものがないので、たとえ意味は理解できても、心の中に深くしみわたりにくい」のではないでしょうか。
一方、目で見た光景というものには、何かしらの感情が芽生えるものです。感動したり、腹立たしかったり…
だからこそ、記憶により深く刻まれ、思い出しやすくもなるのだと思われます。
ですから、記憶をより長く維持するするためにも、文の内容を頭の中でイメージして映像を作り上げ、それを「見る」ことをおススメします。
そして記憶を呼び起こす際には、その映像が自然と浮かび上がってくることでしょう。
あとに重要な文章が続くことを示す語句に敏感になる
日本語の文章の場合でも、たとえば「つまり、~」・「しかし、~」・「実は、~」などの言葉の後には重要な内容が続きますよね?
これらの言葉の後には、筆者や話者が相手にしっかりと伝えたい内容が含まれるわけです。
英語でも同じことが言えます。
- 「つまり」→「therefore」
- 「しかし」→「however」
- 「実は」→「in fact」
などを文中で見つけたら要チェックで、その後に続く内容をより深く理解・記憶するようにしていきましょう。
そして、このことはリスニング問題でも同様です。問題でその場所が関係するか、直接問われる可能性が高いです。
上記のような単語は他にもたくさんあります。その他の具体例についても、今後紹介していきたいと思います。
ちなみに「for example(たとえば)」や「such as(たとえば~のような)」などの後は具体例が続くので、逆にサラッと読めばよいでしょう。
このように、文章中には重要な箇所で慎重に読み進めるべきところと、サラッと読んだり、読み飛ばしてもよい箇所などが混在しています。
それらを判別できるようになって、メリハリのある読み方をすればより効率的に、スピーディーに読めるようになるでしょう。
分からない構文や単語にも慌てず、推測し、無理なら読み飛ばす
TOEICに向けて十分に準備をしてきたとしても、本番ではどうしても分析できない構文や、知らない単語が出てくることはあると思います。
そんなときは決して慌てることなく、「分からない部分は、あって当然!」と気持ちを切り替えてください。
分からない箇所が少々あっても、大体の問題は解けてしまいます。そう心に言い聞かせて、本番では気にしないようにすることです。
そして、訳せないところは前後の文脈などから推測をしてみましょう。それで、推測しても思い浮かばないときは…
読み飛ばしましょう!
ハッキリ言って、1つの文章にこだわっている時間などないです。1つの場所に固執している時間を、次の文章を読む時間に譲ってあげてください。
こうした割り切りができるかどうかが、時間の足りないリーディング問題で最後の問題まで辿り着けるかどうかの分かれ道になるでしょう。
返り読みをしない
おそらくリーディング問題において、塗り絵を可能な限り減らす(理想はゼロ)ための最大の秘訣が、この「返り読みをしない」ことでしょう。
これまで説明した他のPart7対策ポイントは、意識さえすれば比較的すぐに実践できてしまうことばかりでした。
ただ、この「返り読みをしない」という対策は、身に付けるのにある程度時間がかかるかもしれません。
というのも、私たち日本人は、学生時代の勉強や受験勉強の際に、返り読みをする習慣を身に付けてきたのが普通だからです。
では、まずは返り読みとはどういう読み方なのかについて説明していきます。
さて、ここでいう「返り読み」とは、
「まず一文を最後まで読み終えてから、再び先頭に戻り、日本語としてふさわしい訳を考えながら理解していく」
という読み方をいいます。学生時代、そんな風に英語を訳していませんでしたか?
確かに私たちは日本人ですから、日本語に訳すときには日本語の文法で整えられた形に整理して意味を理解したほうが分かりやすいでしょう。
それに、学校のテストや大学受験などで「以下の英文を日本語訳せよ」という問題の場合はそうやって解答するのが普通ですし、そうするべきでしょう。
しかしながら、TOEICのようなスピード読解を必要とする場合や、リスニングする際には、振り返る時間的な余裕はありません。
そのため、返り読みをしてしまうこれまでのクセを取り除いて、
「英語を英語の語順のまま、理解していく」
という新しい体質を手に入れる必要があるのです。
では、具体例を挙げて、返り読みと、英語の語順のまま読んでいく方法の比較をしていきましょう。
< 返り読みの場合 >
The Quest Gallery in Osaka City will host its annual photography contest this spring.
この英文を返り読みをする場合は、まずは TheQuest から this spring までを全部読み終えてから、
「これは The Quest Gallery in Osaka City までが主語で、will host が動詞、its annual photography contest が目的語で、this springが副詞だな。
だから、意味は『大阪市のクエストギャラリーは、今春、年次写真撮影コンテストを主催します。』だな。これでよし!」
といった感じで読んでいきます。日本語訳は、単語を日本語として分かりやすい語順に並べ換えて、整理されたものになっています。
これが、返り読みです。
< 英語の語順のまま読んでいく場合 >
The Quest Gallery in Osaka City will host its annual photography contest this spring.
一方、この英文を英語の語順のまま読んでいく場合は、
「The Quest Gallery『クエストギャラリー』、in Osaka City『大阪市内の』、will host『主催する』、its annual photography contest『年次写真撮影コンテスト』、this spring『今春』、だな」
これで終わりです。つまり日本語訳は
「クエストギャラリー、大阪市内の、主宰する、年次写真撮影コンテスト、今春」
となります。どうですか?これでも十分、英文の意味は理解できるのではないでしょうか。
英語と日本語では文法的に語順が全然違うためにこのような訳し方になりますが、意味をとるだけなら、この語順でも問題ないわけです。
返り読みをした場合と比べて、頭の中で考えなければならない分量が全然違うことが明白ですよね。
当然、語順のまま読むほうが断然スピーディーに読めます。
また、リスニングのように読み直しができない場合でも、話の内容について行くことが可能になります。
これまで返り読みを続けてきた方が語順のまま理解する方法に変更する場合、最初はかなり違和感を感じると思います。私もそうでした。
少しずつでいいので、たまには返り読みをしてしまうそんな自分を許しながら、返り読みのクセを取り除いていきましょう。
なお、英語の語順のまま理解していくための練習方法としておススメなのが「音読」なのですが、こちらは今後の記事で紹介していきたいと思います。
英語を理解するのにスピードが要求される場面では必須ともいえる、この
「英語を、英語の語順のまま理解する」
という読み方・聞き方で、TOEICの壁をぜひ乗り越えていただきたいと思います。
正しく対策して、TOEICリーディングをスコアアップしていこう!
この記事は以上となります。
各Partごとに効率の良い、スピーディーに解いていく方法を紹介しました。参考になったものがあれば幸いです。
ちなみに、各Partごとの時間配分を提案しましたが、これは塗り絵を「ゼロ」にする場合の、理想的な時間配分を指します。
実際に試してみると分かることですが、この時間配分を全てクリアするというのは最初は相当ハードな壁だと思われます。
最初は時間配分をクリアできなくて当然です。それよりも、時間配分を意識することが大切なのです。
意識することで初めて、少しずつ現実を理想に近づけていくことができます。
いきなり塗り絵をゼロにしようと考えるのではなく「どんどん塗り絵を減らしていこう」というくらいの気持ちで取り組んでいけばいいのです。
TOEICは正しく頑張れば、頑張った分だけの結果が返ってくる試験だと思います。
あなたの努力が実って大きなスコアアップを果たされるよう、応援しています!
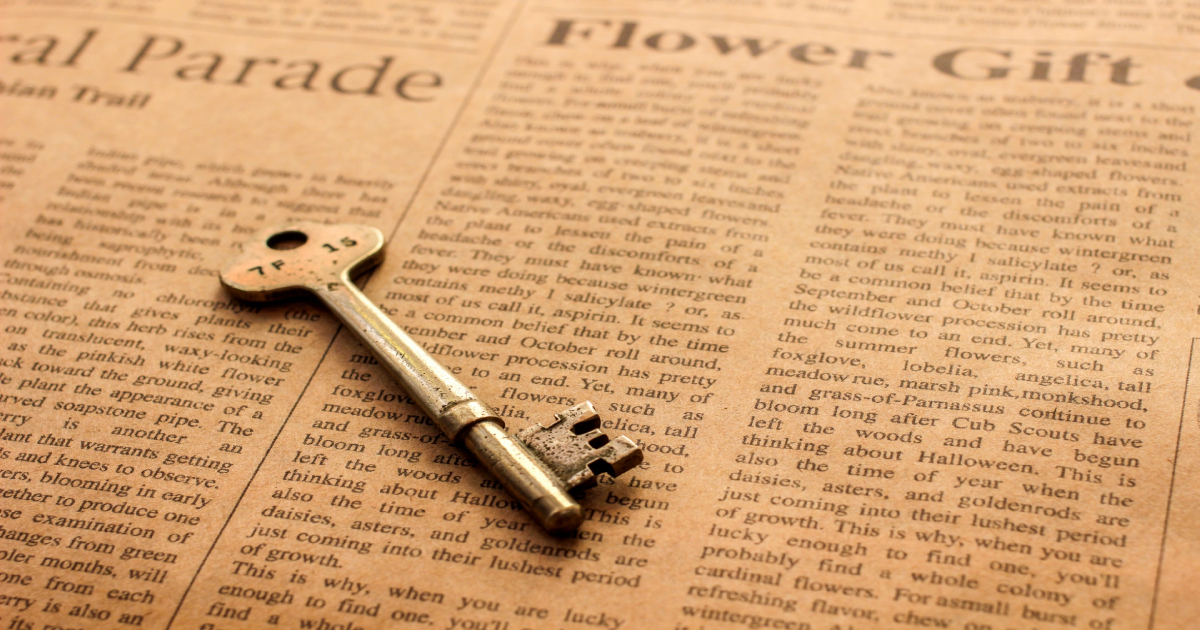


コメント
[…] 時間内に問題が解き終わらない (たくさん塗り絵してしまう・・・)● Part5 の短文穴埋め問題をスピーディーに解くにはどうすれば?● Part5 […]