「TOEICリスニングは、Part3 と 4 が苦手。スピードが速くて、ちょっと何言ってるか分からない…」
「Part 3・4 は解答時間が短い!だから、次の問題の先読みまでする余裕が全くない…」
TOEICリスニング問題 Part3・4 の会話・説明文問題は、リスニング問題全100問中何と69問を占める、リスニング分野のメインパートです。
そのため、ここでの出来がTOEIC全体のスコアに大変大きな影響を与えます。
テストを受けるからには、当然ハイスコアをとりたいですよね。ですが、上の悩みのように Part3・4 を苦手としている人は本当に多いです。
音声のスピードは速いわ、解答時間は短いわ、次の問題の先読みをしないといけないわで、大変です。
ただ、なぜ Part3・4 が解きにくいのかについては原因がハッキリしているので、対策を立てやすいともいえます。
まずは Part3・4 が苦手になる理由を正しく理解し、それに対してしっかりと対策を立てて、実践演習を積みましょう。
そうすれば、実はこれらのパートは苦手分野どころか将来的に得意分野へ転換できる可能性もあります。
私も約3ヶ月間の集中対策でリスニングが 130点アップしましたが、その大部分が、Part3・4 のスコアアップでした。
以前はこれらのパートにひどく苦手意識を持っていましたが、今では得点源になっています。
諦めることは全然ありません。TOEICリスニング Part3・4 を「正しく」恐れて、正しく対策を立てていきましょう!
TOEICリスニング問題 Part3・4 の特徴について
では、Part3・4 の特徴を見ていきましょう。まず Part3 は「会話問題」です。
1対1、あるいは3人での会話の音声が流れます。だいたい 30 ~ 40秒くらいの会話です。
会話の音声が終わると、続けて今の会話に対する設問文の音声が3問流れます。
ただ、問題については問題冊子に記載されているので、流れてくる音声はその文を読み上げているだけです。
会話の数は全部で 13セット、1セットにつき 3問出題されるので、問題数は合計 39問になります。
全 13セットのうち最後の数セットは、図表を伴った問題になります。
会話の場面としては、職場・店内・病院・予約など、様々あります。
一方、Part4 は「説明文問題」です。
1人が、あるテーマについて説明している音声が流れます。
流れる時間の長さや出題のされ方は、Part3 と同じです。
説明文の数は全部で 10セット、1セットにつき 3問出題されるので、問題数は合計 30問になります。
場面については、留守電・工場内のアナウンス・広告・ラジオ放送・セミナーなど、様々です。
Part3 と 4 はその特徴や解き方がほぼ共通するので、両者を1つとみなして、そのスコアアップの対策方法についてこれから1つ1つ解説していきます。
音声を聞く前に、まずは設問の先読みを
1つ目から、最重要ポイントといってもよい、王道の中の王道の対策法を紹介します。それは、
「音声を聞き始める前に、設問文を先読みしておく」
という方法です。
設問文は 3問ありますが、それらを音声が流れ始める前に目を通して、「どんなことが問われるのか」を事前に把握しておくのです。
そうすることで、以下のメリットが手に入ります。
- 何を聞きとれれば正解できるのかが分かる
- 話の内容のおおよその流れを推測できるようになる
- 実際に問題を解くときには、もうすでに設問を読み終えているために、解答時間を大幅に短縮できる
などです。いずれも、かなり魅力的なメリットですね。
この「先読み」という手法は、どのTOEICリスニング教材でも紹介されているほどの超有名なもので、誰もが試みる手法といえるでしょう。
ではここで、先読みするときのポイントを紹介していきます。
Directions の前に、1題目の設問文を先読みしておこう
前の Part が終わって次の Part の1題目の音声が始まる前には、次の Part についての説明の音声である「Directions」が流れます。
その音声が流れている間は、絶好の先読みチャンスです。ここで1題目の設問文をしっかりと先読みしておきましょう。
さらに余裕のある場合は、この時間で図表問題の図表にも目を通しておくのもよいかと思います。
設問文だけ読み、選択肢までは読まないのがおススメ
先読みは設問文だけにとどめておくことをおススメします。
人によっては選択肢まですべて先読みすることを推奨される方もいらっしゃいますが、特にTOEIC初心者の方にはおススメできません。
というのも、そこまで先読みできるほど時間の余裕はないし、選択肢はその中で本文と一致するのは1つだけで、あとは誤った内容だからです。
本文の音声を聞き始める前に、本文と無関係の内容まで頭に詰め込むと、混乱してしまう恐れがあります。
なので私は、先読みは設問文だけにとどめることを推奨します。
「個別問題」のほうを特に先読みしておく
設問の種類は大きく分けて「全体問題」と「個別問題」に分かれます。
全体問題は、たとえば「そのワークショップの主なテーマは何ですか?」といった、話の全体に関わる内容を問うてくる問題です。
一方、個別問題は、たとえば「Jobさんは店員に何を注文しましたか?」といった、話の中の一部分の出来事を問うてくる問題です。
そして、先読みをよりしっかりしておくべきなのは、後者の「個別問題」になります。
全体問題だと、たとえ先読みが不十分でも音声の色々な箇所にヒントがあるため、1箇所のヒントを逃したとしても、致命傷にはなりにくいです。
ところが個別問題の場合は、音声の中で1箇所しかヒントが出てきません。それを聞き逃したら致命傷になってしまうでしょう。
そのため、個別問題をしっかり先読みして、その1ヶ所のヒントを逃さないように努めるのが重要なのです。
具体的なキーワードが出てきたら、要チェック
たとえば設問文の中に「Tuesday」・「this morning」・「$100」などの具体的なキーワードがあれば、要チェックです。
そのキーワードを頭に入れておけば、本文の音声中にそれが聞こえてきた周辺に、解答のヒントが隠されています。とても解きやすくなりますよ。
設問文を読んでストーリー内容が想像できるときは、必ずしておく
設問文を読むことで、話のおおよその流れが推測できる場合があります。
その場合はラッキーだと考え、しっかりと推測してから音声を聞き始めましょう。何の手掛かりもない場合よりずっと気持ちが楽になります。
よく使われる設問文は、暗記しておく
設問文には「よく使われる定型文のような設問文」がたくさんあります。たとえば、
- Why is ~ calling? 「~はなぜ電話をかけているのですか?」
- Who most likely is ~? 「~は誰だと考えられますか?」
- What is the main topic of the ~? 「~のテーマはなんですか?」
などなど。これらの頻繁に出てくる定型文のような設問文は、読んだ瞬間に意味が伝わるくらいにしておけば、先読み時間を短縮できます。
「ちりも積もれば…」です。こういった些細なものと思われる努力が積み重なって、大きな時間短縮につながっていきます。
次の問題の先読みをするタイミングは?
当然ですが、先読みをするにもある程度の時間が必要です。では、具体的にどのタイミングで次の問題の先読みを始めるべきかというと…
3問目の音声が流れ始めたとき
が理想です。それまでに3問全てを解き終えておき、3問目の音声が流れている13秒間と、次の問題の音声が流れる前のアナウンス
「Question ~ through … refer to the following -----.」
が流れている間までの時間で、先読みをしていきましょう。
このタイミングが、解答時間の確保と先読み時間の確保との間の、ベストなバランスだと考えられます。
本番で先読みをする余裕がないときは…
先読みの話はこれで最後になりますが、少し、元も子もないことを言います。
本番で先読みする余裕がないときは、無理にする必要はない
驚かれたかもしれません。これまで先読みの重要性を延々と語ってきたのに、結局先読みしなくてもいいのか、と。
いいえ、先読みの重要さは先人の誰もが知るところで、私も、その必要性は十分に認識しているつもりです。
ここで強調したいのは、「無理に」する必要はない、ということです。
本番では、緊張したり、予想外の事態が起こったり、はたまた、まだ先読みの技術が体に染み付いていないなど、諸々の理由で、
先読みしたくてもできない
という状況は十分に考えられるわけです。
TOEICの常識的なセオリーとして、先読みをするのは当たり前、先読みしなければハイスコアなどとれないという考えが確立されています。
ただ、その考え方に固執し過ぎるあまり、本番で先読みができなくなったときにパニックになったり、
「もうだめだ、リスニングは諦めよう」
ということになってしまうのが一番残念だと思うのです。
これは私の体験なのですが、本番で、約8割の問題で先読みができなかったことがありました。解答に時間がかかって、先読みする余裕がなかったのです。
ただ、なかなか先読みができない分、より必死になって音声に集中するようにしました。
そして本番で問題を解きながら実感したのは、
「たとえ先読みできなかったとしても、どうにかなる問題はかなり多い」
ということです。
確かに先読みができれば、より一層正答率は上がると思います。ですが、先読みできなかったとしても、
「話の全体の流れ」や「話者の目的や要求」
などを聞き取ることができれば、大方の問題を解くことは十分可能だと思います。
実際に、8割の問題で先読みができなかったときの私のリスニングスコアは 410 / 495 でした。
そもそも今ほどはまだリスニングに自信がなかった頃で、しかも8割先読みができなかったとしても、このスコアを獲得できたのです。
普段からTOEICのスコアアップのみならず本物のリスニング力を磨いている人であればなおさら、先読みに頼らなくても何とかなると思います。
まとめると、
「先読みはスコアアップに多いに有効。しかし、できない時でも悲観せず、話の流れや目的さえ捉えられれば、問題なく解けることが多い。」
これが、私の考えです。先読みできない状況なのに「無理に」しようとする必要はないと思っています。みなさんは、どう考えますか?
「音声を聞きながら設問を解く」のはアリ?
Part3・4 の解法の1つとして、
「音声を聞きながら、設問を解いていく」
という方法があります。「マルチタスク」とも呼ばれます。
音声を聞いていて、設問に関係する箇所を発見したら、その都度答えをマークしていく、という手法です。
この方法だと、本文の音声が終了した時点で既に全ての問題を解き終えているので、先読み時間を存分にゲットできます。
なるほど、ムダのない、効率的な手法だと思います。
しかし、この解法を利用できるのは、かなりのリスニング熟達者に限定されるでしょう。
なぜなら「音声を聞きながら解答する」には、正解の選択肢を選んでマークをしている間も正確にリスニングができることが求められるからです。
かなりの上級者でないと、この「マルチタスク (複数の作業を同時に行う)」のレベルの仕事はこなせないでしょう。
やはり、上級者以外の人は、音声が流れている間は、その音声を聞くことに集中するべきだと思います。
音声の冒頭部分には大きなヒントがいっぱい!
本文の音声を聞くときは、まず、その冒頭部分に集中しましょう。そこには音声全体に関するヒントが盛りだくさんです。たとえば、
- 登場人物
- 人物間の関係
- 場面
- 話のテーマ
などが冒頭部分で示されます。これらをしっかり聞き取りましょう。
それができれば、その後の話の流れをある程度推測することも可能になって、理解がよりスムーズになります。
なお、これは Part4 に限ってのことですが、本文の音声が始まる前のアナウンスで
「Questions ~ through … refer to the following --------」
と赤線の部分が Part3のような「conversation」限定でなく、具体的な場面設定を教えてくれる単語が入ってきます。
たとえば、赤線部分には
- telephone message「電話のメッセージ」
- news report「ニュース報道」
- excerpt from a meeting「会議の抜粋」
などの語句が入ってきます。
Part4 では一番最初にこの部分に注目し、話の場面設定を把握しておくようにしましょう。直後に始まる音声内容がとても理解しやすくなります。
話の目的が何かを見つけよう
Part3・4 は、2 までと異なり、
「長文を聞いてストーリーを “大まかに” つかむ力」
が求められます。細部にわたって隅々まで内容を理解することまでは求められていません。
それは、設問の内容が話の概要についてのものばかりであることからも明らかです。
そのため、音声を聞いている間に意識すべきことは、話全体の流れと概要を把握して、
「話の目的は何なのか」
を見つけることです。
それは相手に何かをして欲しいといった要求だったり、はたまた話し手がしたがっていることを伝えることであったり、様々です。
目的を捉えられるよう、アンテナを張りながら聞いていくことが大切です。
なお、特に Part4 では、話の最後に話し手の目的や主張が判明することがあります。
その場合でも、自分なりに「~ということを求めている (主張している) のではないか?」と予測しながら聞いていくといいでしょう。
キーワード・フレーズで全体像を把握する
上で述べた「話全体の流れと概要を把握して、目的をとらえる」ために有効なのが、「キーワード・フレーズ」を見つけることです。
話の中で繰り返し登場する語句はまさにキーワードで、その話の全体像を表しています。
また、たとえば
- Would you mind ~ing?
- I was wondering if ~.
といった「~していただけませんか?」という依頼のためのフレーズが出てきたときには、そこに話全体の目的が示されていることが多いでしょう。
そのような語句・キーワードに敏感になっていくと、全体像を把握することができるのです。
話の「流れ」を意識する
話には、一定の「流れ」があります。その1つを以下に示すと、
- 導入 → 2. 問題発生 → 3. 要求や提案 → 4. 意思決定
の流れです。具体例を示すと、
- 導入「大家さんですか、こちらは202号室の もょもと です。」
- 問題発生「給湯器からお湯が出なくて困っているんですよ。」
- 要求や提案「ちょっと、ガス会社に見てもらえないですかね?」
- 意思決定「ちゃんと対応してもらえないなら、家賃の支払いを保留します。」
何とも強気な借主ですね (笑) 。このような流れも考えられるでしょう。
これらの要素を区別して聞いていくことで、話の流れがより鮮明になり、内容の理解度が上がっていくのです。
音声の内容を頭でイメージして、映像化しよう
「音声は 30~40秒も流れてくるので、問題を解くころには最初のほうの内容を忘れてしまっている…」
そういうことはありませんか?
Part2 までは短い音声だったので心配無用でしたが、Part3 からは音声が長くなるので、こうした悩みが増えることになります。
では、どうしたら記憶を維持できるようになるかというと、それは
「聞こえてくる音声の内容を頭の中でイメージして、映像化する」
ことで可能になります。
では、この「イメージして、映像化する」ことの具体例を挙げると、
Hello! Can I bring you something to drink? 「こんにちは!何か飲み物をお持ちしましょうか?」
Thank you. I’ll have a beer then. 「ありがとう。じゃあ、ビールをお願いします。」
という音声が流れた場合、まずは飲食店の店内をイメージして、さらに客が店員にビールを注文している姿をイメージして、映像化するのです。
店内の装飾や、客や店員の性別・容姿などは自由にカスタマイズしてください。
一度きちんとイメージしておけば、30~40秒後にその映像が全く浮かんでこないということはまずないはずです。
そのようにすれば記憶できる時間を延ばすことができるので、これからは耳にしたことを頭でイメージ映像化していくクセをつけていくとよいでしょう。
なお、この「イメージ映像化」という手法は、TOEICリーディング問題 Part7 読解問題でも大いに力を発揮してくれます!
「3人問題」について
Part3 の会話文は、その多くが 2人の話者による会話ですが、中には話者が 3人登場する問題もあります。
「2人でも聞き取るのが大変なのに、3人なんて!」と悲嘆に暮れる人もいるでしょう。
ですが、別に 2人が 3人になろうとも、会話全体の概要や目的を捉えるという、するべきことは同じなので、それほど難易度は変わりません。
ただ、3人問題に特有のポイントがいくつかあるため、以下に紹介しておきます。
最初のナレーションで 3人問題だとわかる
会話の音声が始まる前のナレーションで、
「Questions ~ through … refer to the following conversation with three speakers.」
と流れるため、この時点ですぐに3人問題が流れることが判明します。心の準備ができますね。
必ず2人が同性。3人同性はない
3人問題では、必ず 2人が同性となります。3人とも同性となる問題はありません。
ですから、たとえば
What information does the man ask for?
という設問文を見たときに、即座に、この会話は「男性が1人のケース」だということが判断できます。
なので、3人の中で男性の発言に特に注意しておけば、この設問を正答しやすくなるわけです。
3人の関係や立場を捉える
3人問題の場合、可能な限り 3人それぞれの関係や立場を捉えるようにしていきましょう。
たとえば「女性が医者で、男性が患者」など、性別で分けてとらえる程度で十分だと思います。
ここで「あれ、もう1人は?」となりますが、3人中 2人の関係が分かれば残り 1人も推測しやすくなりますし、自然と判明することも多いでしょう。
まずは 3人中 2人でいいので、男女の別で、関係や立場をとらえるようにしていきましょう。
名前にこだわらなくても正答できる問題が多い
TOEICの教材の中には「3人問題では、登場人物の名前を覚えて、各人の発言内容を聞き分けていくとよい」としているものがあります。
ですが、おそらく、特にTOEIC初心者の方の場合にそこまで要求するのは酷だと思われます。
確かにそこまでできれば理想でしょうが、それができるのは、余裕を持ってリスニングできるレベルに既に達している人に限られるでしょう。
一般の受験者の場合は、名前を覚えようと必死になるあまり、肝心の話の流れを見失ってしまって、本来解けた問題もミスしてしまう恐れがあります。
…心配には及びません。ハッキリ言って、名前を覚えられなくても「会話全体の内容や目的」さえ捉えられれば解ける問題がほとんどです。
また、たとえ設問文に人名が出てきた場合でも、「消去法」を用いることで、少なくとも正解にはたどり着けることのほうが多いです。
ですから、3人の名前を覚えきるような芸当は、余裕を持ってリスニングできるようになってからで十分だと思います。
「発言の意図を推測する問題」について
昔のTOEICでは見られなかった問題形式で、Part3・4 の問題の中では1番解くのに厄介だといわれている問題があります。
それが「発言の意図を推測する問題」です。たとえば、
Why does the man say, “This place isn’t appropriate for us to have dinner in”?
「男性はなぜ “この場所は私達が夕食をとるのにはふさわしくない” と言っているのですか?」
というものです。
他の設問とは違って、質問がストレートではなく、話し手の気持ちを推測して答える必要がある分、難易度が上がります。
推測のヒントとなるのは、
- 発言の前後の文脈
- 話の全体の流れ
- 話し手の置かれている状況
- 声のトーンや、話し方
などが挙げられます。このうち特に「発言の前後の文脈」が一番のヒントとなります。話の流れを正確に追うことで、正しい推測が可能になります。
なお、話の流れが正確につかめれば、たとえ推測できなくても、消去法で、明らかに間違っている選択肢を消去して正答することも可能です。
他にも話し手の置かれている状況や、声のトーンなどで、少なくとも発言が積極的なものか、消極的なものかの判断が付きやすくなるでしょう。
これらのヒントを参考に、話し手の気持ちを推察して解答しましょう。
図表問題について
Part3・4 ともに、最後の数題では問題用紙に図表が掲載された問題が出題されます。
人によっては図を見た瞬間に「うゎ、難しそうだな…」とネガティブな心情を抱くと思います。
ですが、むしろ逆に「あ、ヒントくれてる。よし、解けるぞ!」というポジティブな気持ちで挑んだほうが良い結果が出るはずです。
ちなみに私は苦手意識はありません。サービス問題と感じるときもあるくらいです。
実際、図があることで、話のテーマや場面が見えてきます。しかも、具体的な数字や物の名前なども表示されているのです。
ヒントだらけだと思いませんか?
通常の問題では、特に Part3 では全くのノーヒントで会話が始まるわけですから。Part4 でも場面についてのアナウンスが1度流れるだけです。
この点、図がある場合は、何度でもヒントをチェックできてしまいます。これを利用しない手はありません。
最初は慣れない表問題に戸惑うと思いますが、次第に、意外に図表問題は解きやすいなと、実感できるのではと思われます。
なお、図表の中で特徴的だと思う箇所はチェックしておきましょう。たとえば商品カタログの場合なら、
- 1番高価な商品
- 割引されている商品
- 品切れとなっている商品
などが考えられます。そういった箇所はかなりの高確率で音声で触れられるので、意識しておきましょう。
設問文の音声は無視して、できるだけ素早く解いていく
TOEICリスニング問題は、本文だけでなく、設問文まで音声を流してくれます。ですが、それは全く聞く必要はありません。
設問文は問題用紙に書かれていて、音声はそれをただ音読しているだけだからです。
設問文の音声は 5秒間、選択肢を検討する時間は 8秒間です。
なので、設問文の音声を耳に入れてから選択肢を検討し始めると、選択肢を全部読んで答えを選んでマークするまで 8秒しかありません。
やはりここは、本文全体の音声が終わった瞬間に、音声は無視して1問目の設問を「読み」始めましょう。
そして、1問分に割り当てられた 5秒 + 8秒 = 13秒よりも早くマークし終えることを意識しながら、一気に素早く解き終えるようにしましょう。
理想は、3問目の設問文の音声が流れ始めるころには3問とも全て解き終えている状態です。
そうすれば、次の問題を先読みする時間が生まれるからです。
問題を解く順番について
今から話す解法は、もしかすると他の人で実践している人は少ないかもしれません。
少なくとも、私がこれまで読んできたあらゆるTOEIC関連教材の中に、この解法が紹介されているのを見たことがないからです。
私自身が、どうすれば正答率を上げられるかを常に考えながら問題演習をこなしていたときに、ふと思いついたのが、この解法です。
私自身はこの解き方を実践して、苦手だった Part3・4 に対する気持ちがずいぶん楽になって、しかも正答率がグンと上がりました。
ですから、自信を持ってこの解法を紹介したいと思います。
それは、
「設問の3問目から解く」
という方法です。
つまり、本文の音声が終わった後、1問目からではなく3問目から先に解き終えてしまう、ということです。
3 → 1 → 2問目の順番で解くことになります。
なぜそのような解き方を勧めるかというと、3問目の設問の内容は、本文の内容の終わり周辺に関するものだと想定されるからです。
そしてその根拠は、設問で問われる内容は、本文の内容の順番通りになっているからです。
ということは、3問目はちょうどたった今耳にした内容について問うてきているわけですから、記憶が一番鮮明なときに解けてしまうわけです。
「今」ならすぐに解けてしまうのに、それを避けてわざわざ後から解く必要があるでしょうか?
この方法なら、3問目の正答率がグンと上がるのは言うまでもありません。しかも記憶が鮮明なので、あとで解くより素早く解くことができます。
これが 1 → 2 → 3問目の順番通りに解いていくとしたら、3問目を解こうとしたときには、記憶の鮮度が落ちているわけです。
すると、もしも 3問目から解いていれば正答できた問題をミスしてしまう可能性があります。
なので、まずは3問目を瞬時に解いてしまって、それから 1問目へ戻って解いていくという解法は、個人的に大変おススメです!
正確なマークは、Part4 まで全て解き終えてから
Part3・4 の音声が流れている間は、やるべきこと、意識するべきことが盛りだくさんです。
ハッキリ言って、マークシートを丁寧に塗りつぶしている時間の余裕はないのが通常でしょう。
ですから、問題を解いている間は、マークシート内の正解と判断した箇所にチェックか何かを入れておくだけにしておくことをおススメします。
そして、Part4 が終了してリーディング問題に移る前に、それらをまとめて丁寧に塗りつぶしていくわけです。
この方法で、より一層リスニングに集中することができるようになります。
ただし、ご想像のとおり、この方法だとリーディング問題を解く時間が最大で 3分ほどつぶれてしまいます。
そのため、今度はリーディング問題のほうに負荷がかかってしまいます。
なので、このあたりは自分のリスニングとリーディングの実力を比較して、どちらにより多くの時間をかけるべきかを見極める必要があるでしょう。
見極めたら、その程度によって、リスニング解答時にどれくらい正確にマークシートを塗っていくかの「さじ加減」を決めていくとよいでしょう。
あなたを励まします
これまでこの記事では、たくさんの Part3・4 の対策法を伝えてきました。
ここまで一通り読んでくださったとしたら、その量の多さを実感してもらえたのではないかと思います。
これらの紹介した対策を全てしっかりと実践していったとしたら、確実に大幅なスコアアップを果たせることでしょう。
ですが、対策の数は多いですし、中には一朝一夕では身に付かない対策もあります。
そして、多くの人が、本来やるべき対策の一部分のみしか身に付いていないまま、本番に臨むことになるでしょう。私もそうでした。
もしもあなたが、なかなか自信を持てないまま本番を迎えてしまったときは、よろしければ以下の話を頭に入れてから、本番に挑んでください。
あなたを励ましたいと思います。自分の実体験から、体で覚えたことです。
話の「流れ」
Part3・4 では、たとえ話の内容が多少勘違いして理解していたとしても、
話の「流れ」
さえ合っていれば、正解に辿り着けることは多いです。
キーとなる単語
また、たとえ話の内容が見えてこなかったとしても、
キーとなる単語
さえ聞きとれていれば、それらを組み合わせて話の流れを推測することで、正解に辿り着けることは多いです。
あきらめない
そして、たとえ途中でキーとなる単語すらも聞きとれないくらい訳が分からなくなっても、
あきらめずに、せめて最後の 1~2文だけでもしっかり聞き取ろう
という気持ちで臨めば、3問目に正解できることが多いです。
問題は、解ける
今述べた「励まし」は、結局何が言いたいのかというと、
内容がよく分かっていなくても、解ける問題はたくさんある。だから、途中であきらめないでほしい
ということです。
これは、Part3の受験中に、あまりに聞こえなさ過ぎて、自信を喪失し、茫然自失した経験のある昔の自分自身に対しても伝えたい言葉です。
どれだけ音が判明せず、意味内容も不明でも、とにかく最後まで必死にもがいて、あがいて、何らかのヒントを見つけられるように集中しましょう。
その姿勢だけでも、きっと正答率に大きな違いが現れることでしょう!
頑張ってください!応援しています!

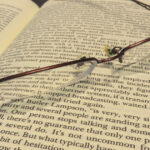

コメント
[…] ● Part3・4 の会話・説明文問題での正解するコツが知りたい! […]